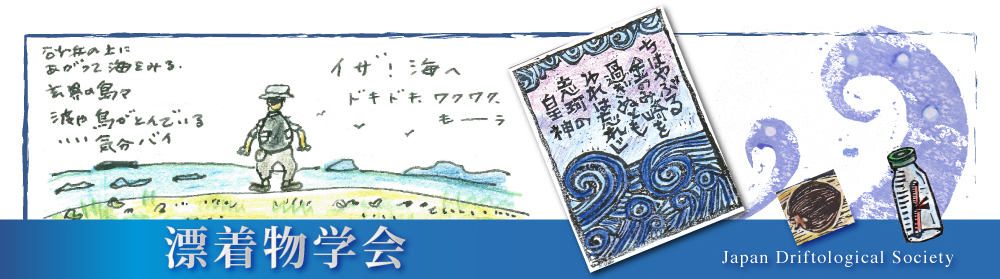会員が出版した漂着物やビーチコーミングに関する書籍を中心にご紹介します。
 海とヒトの関係学2「海の生物多様性を守るために」
海とヒトの関係学2「海の生物多様性を守るために」
編著:秋道智彌・角南篤,西日本出版社 2019年発行
この本は,これまでにOcean Newsletter誌に掲載された文の中から,海ごみ問題と,海の生物多様性に関わるものをまとめたもので,特に前半にある「海のゴミ問題を考える」では,今話題になっているプラスチック汚染などに関わるものを多く取り上げています。この本には,漂着物会長の中西弘樹先生の「漂着物に取りつかれた人たち」と,編集委員長の鈴木明彦先生の「海岸漂着物から地球環境を読む」の2編が掲載されています。タイトルは異なりますが,どちらもビーチコーミング学への案内でとなっています。(どんぶらこ62より一部抜粋)
貝と文明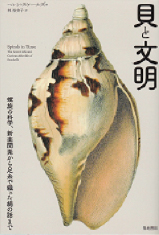
ヘレン・スケールズ著,林裕美子訳,2016年,築地書館発行,定価:2700円+税
著者のヘレン・スケールズは,イギリスの海洋生物学者で(原題Spirals in Time),貝・イカ・タコ(アオイガイ)などの軟体動物やオウムガイについての研究業績や保全活動がわかりやすく紹介されます。日本では,貝は食べておいしいかどうかに目が行きがちですが,殻の色や模様や形についての研究の紹介,貝殻が奴隷貿易に使われたいきさつ,イガイ類やタイラギ類が貝殻を固定させるために作る足糸を使った織物の話,繊細な「海の蝶」を捕食する獰猛な「海の天使」(クリオネの仲間)の話など,広い海の世界へいざなってくれます。
砂−文明と自然
マイケル・ウェランド著,林裕美子訳,2011年,築地書館発行,定価:3000円+税
ビーチコーミングにとって砂や砂浜は黒子のような存在ですが,砂浜なしではビーチコーミングもできません。砂一粒の物語に始まって,そもそも砂とは何なのか,どのように砂浜や砂漠ができるのか,そして宇宙の砂の話まで,壮大な砂の物語です。
北海道の海辺を歩く−ビーチコーミング学入門
鈴木明彦著,2016年,中西出版発行,119頁,定価:1200円+税
本書は,漂着物の収集であるビーチコーミングを少し深めて科学的に捉えるための入門書であるばかりでなく,北海道の漂着物の図鑑である。さらにアオイガイの生態や打ち上げ貝の海洋生物地理学,鳴き砂の特徴とその起源などはかなり専門的な内容をわかりやすく解説し,巻末の文献リストも含めて,専門家にとっても役立つ内容となっている。また,南方系の漂着果実・種子については,最新のデータを基に漂着分布図を示されている。会員にとっては必読の書と言えるだろう。
1章:ビーチコーミング学への誘い,2章:漂着物の自然史,3章:漂着物の文化史,4章:自然史学的アプローチ,5章:アウトリーチ活動,6章:ビーチコーミング学の展望と課題
「魅惑的な暖海のクラゲたち」~田辺湾(和歌山県)は日本一のクラゲ天国~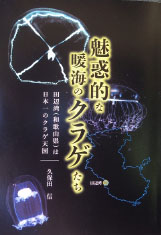
久保田 信著,2014年,久保田研究室発行,販売所紀伊民報,167頁,定価:1000円+税
クラゲの研究で有名な著者が,これまでの経験を基に著者の務める京都大学臨海実験所がある和歌山県田辺湾で見られる,あるいは見られそうなクラゲ各種をわかりやすく解説したものである。エチゼンクラゲをはじめ,カツオノエボシ,カツオノカンムリなど漂着生物として知られている種も多く,この本を手にすると,漂着クラゲに一層目が向くことになるだろう。掲載されている種類は,西南日本に見られるほとんどのものが含まれている。専門的なクラゲの図鑑も出版されているが,本書は写真や図も多く,専門外の者にとっては図鑑としても役立ち,漂着物に興味がある人にお薦めの本である。
長崎県植物誌
中西弘樹 著 長崎新聞社,¥9,870- 2015年,387頁
本書は長崎県に自生あるいは野生化している高等植物についてまとめた植物誌である。長崎県の植物相について,植物地理学的に重要な48種について分布図を示しながら解説し,各地域の植物では,県内を12の地域に分け,植物相の地域的特徴を解説している。植物目録では,新しい分類体系(APG分類体系)に基づき,分類・配列し,種,変種等を含めて,約2700種類が記載されている。この数はこれまでまとめられていたものと比べて,約500種類が新たに追加されている。目次は,Ⅰ長崎県の自然環境,Ⅱ長崎県の植物の概要と植物地理,Ⅲ県内各地域の植物,Ⅳ植物天然記念物,Ⅴ長崎県植物目録,Ⅵ引用・参考文献,Ⅶ索引である。
科学が好きになる22のヒントと実践
横浜市サイエンス研究会著 東京書籍,¥1,296-
本書はヤングサイエンス選書の一つで,横浜市中学校理科研究部会の教師の有志が集まって分担執筆されたものである。「2章 サイエンスホビーを楽しもう」に本会会員大我さんがこれまで実践されてきた生徒たちとの海岸漂着物観察について書かれたものがあります。
1.海岸で漂着物を拾おう!
2.漂着物紹介
3.漂着物クイズ
4.人工物が環境問題に
理科の先生や理科教育に興味のある方にお勧めしたい本である。
「ビーチコーミングをはじめよう 」海辺の漂着物さがし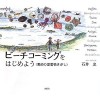
石井 忠 著 木星舎 ¥1,890-
漂着物学会ウエッブサイト/ビーチコーミングとはに掲載されています「少年少女のための“ドンブラッコ”講座」に加筆されたやさしいイラスト満載のステキな本。さあ、海にでよう!海岸を歩こう!春、夏、秋、冬——海からのメッセージをさがしに。海流に乗ってきた椰子の実、砂に埋もれたイルカの骨、不思議なアオイガイ、渚に流れ着いた丸木舟、砂が削ったガラス瓶、異国の陶磁器片……いろんな漂着物 が語りかける、教えてくれる、自然、社会、民俗、アート……そして地球のこと。漂着物博士がわかりやすく案内するすてきなビーチコーミング。
新編・漂着物事典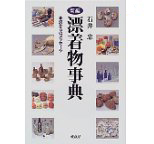
石井 忠 著 海鳥社 ¥3,800-
漂着物に関する本を一冊・・・と言われたら、迷わずコレ!
漂着物学会・初代会長の石井先生の名著である。単行本や文庫本でも知られた漂着物事典の総まとめが、1999年に発行された本書。この本で、石井先生は漂着物学会の設立を暗示されていたが、この本がなければ漂着物学会は無かったかもしれない。
漂着物考−浜辺のミュージアム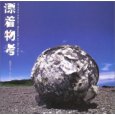
石井 忠 他 著 INAX BOOKLET (2003/10)¥1,575-
海流に乗って辿り着いたさまざまな漂着物を通して、国境や学問分野を越えた驚くほどに豊かなメッセージを伝える。漂着物学会のメンバーが各ページを執筆しました。
海ゴミ-拡大する地球環境汚染
小島 あずさ,眞 淳平 著 中公新書(2007/7)¥861-
漁網が多数漂着する世界遺産・知床。海外からのゴミが流れ着く南西諸島。日々,特殊車両を使わないとゴミを除去しきれない湘南海岸・・・。いまや日本のすべての海岸が,大量のゴミで覆いつくされようとしている。それらのゴミはなせ発生し,どこから来るのか。また,私たちの生活や生態系にどのような影響を与えつつあるのか。そして,いま求められてる対策となにか。忍び寄る海ゴミの脅威の実態に迫る。
漂着物学入門−黒潮のメッセージを読む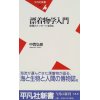
中西 弘樹 著 平凡社新書 ¥714-
日本の浜辺に海流に乗って打ち寄せられる漂着物はヤシなどの植物の実から動物の遺体、そして国際政治を象徴する宣伝物まで実に様々だ。そこから知る海と生物と人の博物誌。
海辺の漂着物ハンドブック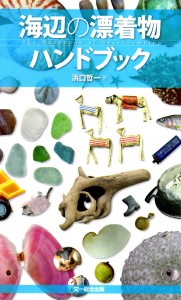
浜口 哲一 著 文一総合出版 ¥1,260-
漂着物やビーチコーミングについてのコンパクトな入門書です。ビーチコーミングで拾える物がどこに由来し、どんな楽しみ方ができるかを紹介しています。浜辺に持って行くにもかさばらず、ビーチコーミング初心者に重宝する本です。
海辺で拾える貝ハンドブック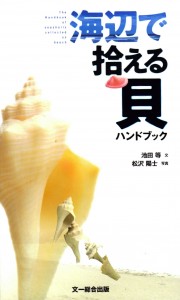
池田 等 著 文一総合出版 ¥1,470
海辺で普通に拾える貝殻150種を掲載しています。打ち上げられた貝には、割れたり、すり減ったりした貝殻も多いのですが、様々な写真が載ってますので、貝殻の名前調べに役立ちます。ビーチコーミングにぜひ持って行きましょう。
Beachcombing for Japanese Glass Floats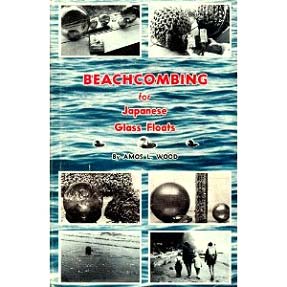
Amos L. Wood 著
1970年代後半、大学生の時に初めてビーチコーミングと言う言葉を知ったのは、この本のタイトルからだった。第一印象は、スゲぇ!外人が日本の浮き玉のことを本にしたんだ。作り方まで載ってるぞ!その後、浮き玉を取り上げたいくつかの本が出ているが、これを超えた本は無い。はるか海の彼方から漂着した浮き玉からこれだけの本を書かれたウッドさんの探究心は、まさに漂着物学の真髄である。古書がアマゾンなどで入手可能。
World Guide to Tropical Drift Seeds and Fruits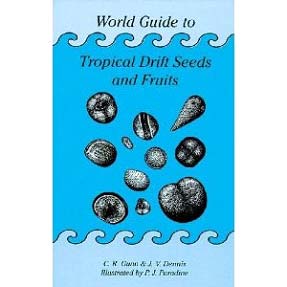
Charles R. Gunn、John V. Dennis著
漂着種子・果実を取り上げたフィールドガイドの中で最も分かりやすいのがこの本。後に写真によるガイド本も出ているが、掲載種全てを細密イラストで表現した本書は,特徴がつかみやすく、1976年初版発行だが、今でも色褪せることはない。1999年にリプリント版も発行され、今でもアマゾンなどで入手可能。